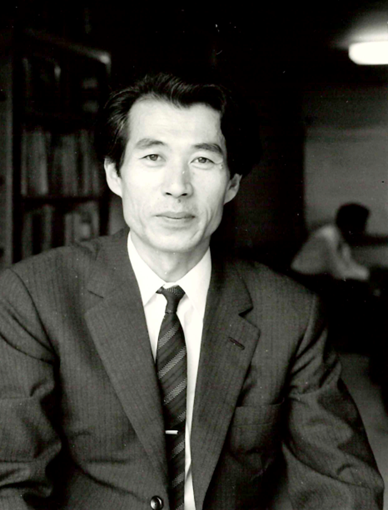
楽観的なことをいうようだが、不思議なことに、あなたが人を理解するため努力する姿勢をもちつづけることが、闇を光に変えることになっていく率は、きわめて高いのである。つまり、そのようなときに、現われ、にじみ出てくる、ある何かが、人間のコミュニケーションの断絶という闇から脱出する、きわめて狭いが、しかし確実な出口となるのではないかと思う。(鈴木成裕)
理解する姿勢をもちつづけよう
さて、人と人との関係は、嵐の夜の電灯のまたたきに似ている。ついたり消えたり、消えたりついたり、われわれの視野は、その度に、明るくなったり暗くなったりする。
人と人との理解も、あるときは相手を理解していると思ったり、また理解されていると思ったり、またあるときは、相手に理解されていないと思ったりするものである。いい人間関係をもち、いい管理を行なえば、人と人がお互いに理解し合い、良い人間関係を持ちうると考えたら、大まちがいである。
こういう事情だから、たえず、人はよい仕組みをつくり、よいコミュニケーションになるよう心掛け、また、いつも人間の心を理解しようとする姿勢をもちつづけなければならないのである。もし、そうでなければ、初めから暗闇の中で、ものを捜すような、お先まっくらな集団行動になってしまうわけである。
だから、人を理解できるから理解するのでなく、理解できないから、そう努めるのであるといった常識のうえに立ってほしいものである。
そんな考え方が、仲間同士のぶつかり合いや断絶を少なくし、また、ときどき起こる人間関係の悪化の中で耐えて、集団の一員となることを可能にするのである。
もちろん、人と人との関係なんて、そんなものさ、とさとりすましていてほしいということではない。その事実から、どういう自分の行動をあみ出すか、どういう努力をするかということを考え出すことが、人間的だということである。目の前の暗闇を、自分以外の力によって指導し、リードすることによって明るくしてもらう、そういうような心や行動の位置に居つづけることは、あなた自身が、無機的な存在に変わってしまうことである。
楽観的なことをいうようだが、不思議なことに、あなたが人を理解するため努力する姿勢をもちつづけることが、闇を光に変えることになっていく率は、きわめて高いのである。つまり、そのようなときに、現われ、にじみ出てくる、ある何かが、人間のコミュニケーションの断絶という闇から脱出する、きわめて狭いが、しかし確実な出口となるのではないかと思う。
人間主義経営の基礎となるもの
そして、その努力に疲れ果てたならば、ぐっすりと眠ることである。一夜明けたとき、われわれの意識は、新しい挑戦に耐える力を取り戻しているかもしれない。どうしてもよい人間関係や相互理解を直接につくることが駄目な場合、あなたは、自分の力を過信せず、人間関係の背景となるよいシステムづくりに専念することがよいのではないか。管理の体質を人間的にもっていくのである。
もちろん、努力の放棄が、それで終わるという意味ではない。
暗闇の電灯の点滅が、ひどく人を不安と動揺におとし入れるように、人間関係の中には、そんな状況が、つねにつきまとうものである。
このような状況から、もっとよい関係にもっていく努力をリーダーが払うことが、リーダーが人間に尽しているということである。それが社会への貢献とか、企業が人間をつくっていくといった考え方の根底をつくっていくものである。
もちろん、人間主義経営といわれる考え方の基礎も、そこにあるはずである。あなたの周辺を見ていただきたい。そんな経営者や管理者は、必ずいるものである。その人たちは、欠点の多い人たちであろうが、そこにある姿勢に、ある意味をみつけていただきたいものである。
出典:『集団学入門』((社)日本能率協会昭和四十七年)
