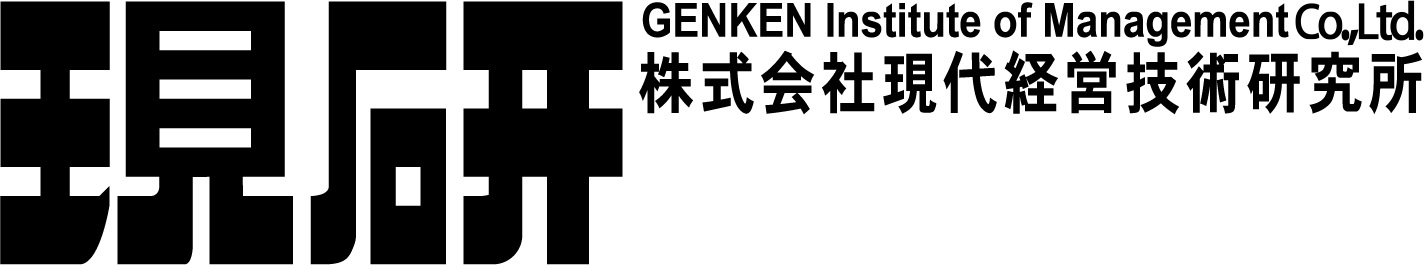(Ⅰ)現研の創立と組織基盤の確立
昭和40 年~49 年(1965~74年) ―戦後の終焉と高度成長の持続―
◇現代経営技術研究所
S.40・7・1 現代経営技術研究所 設立 日米講和条約の発効、日本の独立から13年が経ち、昭和は40年代を迎えました。戦後を脱した日本社会には、一気に、日本人による日本企業の建設とその力によって、日本社会をリードしていこうという気運が強まって来ました。現代経営技術研究所(現研)は、そんな雰囲気の中で、次々と現れてくる新しい事態に対応し、近い将来必要となる日本企業の戦略、企画、計画問題、マネジメント問題等々に関し、企業の助言をする独立系の民間シンクタンクを創設したいという鈴木成裕の意志の下に設立されました。
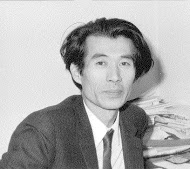
「I E」誌
それ以前、鈴木は(社)日本能率協会において、昭和 34 年に創刊された「インダストリアル・エンジニアリング」誌(S.43 に「IE」誌に変更)の編集に携わってまいりました。同誌は、労使間の衝突を通じて、経営者の中に、これからの企業は受命型行動だけでは支え切れなくなることを悟り始めた人たちが出始めていた時代にあって、勤勉さと効率性、合理性以外の人間性重視の視点を持った新たな現場感覚で、現場を励まし、生産現場に勇気、希望を与え、現場を先導する役割を果たしました。「IE」誌には、“現場を動かす人の雑誌”というキャプションが付いております。 鈴木が同誌の編集長時代に得た体験は、現研の創設、発展の原動力の一つであったことは間違いありません。とくに、その時代に培った多くの方々との相互啓発的な交わりは独立後も続き、鈴木は仕事の上で良い刺激を頂いて参りました。その方々の多くが、既に鬼籍に入ってしまわれました。改めて、精鋭ぞろいの皆々様のご冥福を、鈴木の冥福と共にお祈り申し上げたいと思います。

7O5 研
現研の創立に先立って、この年の1月、鈴木は「7○5研」という研究会を立ち上げました。これは10年後の1975 年あたりで、日本企業は大きな山場を迎えることになるであろうという認識に立って、その時点での日本及び世界の企業環境を予測し、その時点で必要となる人材を育成・確保することを目的とした会合でした。「7○5研」とは、75 年研の意味ですが、7と5の間に○を入れた「ナナマルゴ研」の呼称は、鈴木の命名です。 10 年後の日本にどのような状況が出現するか、アメリカを初め、国際状況はどのように変化し、どのような影響を日本に与えるか等々、日本及び世界の現状と将来を自由に多角的に検討するためのこの研究会は、メンバーは全員20代と30代で構成されました。当研究会において、実際に討議・検討された課題領域は、情報、IE、生産、物流、技術、システム、管理、マーケティング、商品開発、EDP、社会、経済、人間問題等、相当多岐にわたりました。

◇「システム」という新コンセプト
SIP計画
S.42 SIP 計画( System Inspection and Improvement Program):仕事の仕組みの総点検計画と改善プログラム・・・鈴木が開発した業務計画の設定と改善のプログラムです。これは、自分の作業に対して、自主的な点検をシステムで設計された範囲において行い、その点検情報を所定の用紙にグルーピングしてウエート付けをしていくプログラムです。その結果得られた精度の高い情報に基づいて、作業者は確度の高い行動をすることが可能となり、また作業の展開の順序や方法の改善、そして実際の業務自体も改善されることによって、技術者、スタッフにも効率的な行動が可能になる―そのように工夫されたプログラムで、社内研修を通じて多くの社で活用されました。 S.44・6 月 鈴木成裕著「システムの時代」(ダイヤモンド社)刊 S.44・12 月 鈴木成裕著 「システムと人間」-70 年代の幹部行動学-((社) 日本能率協会)刊

「システムの時代」
「システムの時代」は昭和 43 年 2 月から 6 月まで「週刊ダイヤモンド」誌に掲載されたものを単行本化したものです。時代は、当時、EDPと言われたコンピュータの実用化と軌を一にして「システム」という言葉が新しい概念として登場して来た頃でした。本書ではこの登場の背景を分析し、システムの問題こそ、今後のビジネス分野はもちろん、どの分野においても、事態の解決と望ましい方向への推進のカギとなるという鈴木の見解が述べられております。 本書のサブタイトルは“革新型ビジネスを創る思考と行動”です。そして「まえがき」の中には次のような下りがあります。「システムとは何か。それと経営の問題とどう絡み合うのか。経営の構成員としてどのようにシステムを扱い、活用したらよいのか。さらにその前提としての時代や環境の本質は何で、それが次にどんな結果をもたらすか」。「システムには、はっきりしないところがたくさんあるはずです」。 「システム」とは何か。これに関して、鈴木は本文中で、「なんでもシステムであるということは一つの発見ではあっても効用性のある発想であるということは出来ない」と述べた上で、「システムは、ただそこにあるだけのものと、ある目的をもってつくられたものの二つに区分することが出来る」と規定しています。 そして、「われわれの経営は、ある目的のために人為的につくられたシステムであり、経営を支えるいくつかのシステムも、経営の目的のためにつくられたシステムである」と説きます。 さらに「この前提から、経営や行動や管理の仕方や仕事の仕組みのまとめ方や、製品の選択や市場媒体の把握や人事評価の仕組みが決められていかねばならない。という意味は、例えば組織においては、各階層の各部門は、それぞれ上位の部門に与えられている目的を達成するように働くことが自己の目的であるということになる」とし、また上下ではなく、横の関係においても「各部門がそれぞれ与えられた目的を実現することで、最終目的に到達する」と述べております。 そして「このように、最高・最終目的に対応する諸目的が網の目のように上下左右に張り巡らされていることが、とくに複雑な経営システムの特徴である」との見解の下に、したがって、経営システムをつくるということは、一面でいえば、「目的の確定と明確化、目的の指定というデザイン行為である」と結論づけます。 しかし、ここで鈴木は、「目的それ自体では役に立たない。立たせる実態が必要である」と論を進め、ある上位目的を達成させるためには「機能」の働きが必要であると、「機能」の問題を展開します。 まさしくビジネスを創る思考と方法の展開です。 本書ではまた、この昭和 40 年代にあって、システムというものがどのような立場から追求されてきたかについて、次の6 つの立場を挙げ、それぞれに解説が付されております。
① OR あるいはシステムズ・エンジニアリングの立場
② 管理システム的立場
③ 機器設計的立場
④ 作業方式的立場
⑤ 管理のための準則的立場
⑥ コンピュータ・ソフトウエア開発の立場 (いずれも解説は省略)
そして、「これらの立場からなされるシステムの追求は、それぞれオーバーラップしている場合が多いが」として、それについては次のような見解を述べております。 「ある意味では、すべてのフィールドにおいて、システムが求められていることの逆説的表現であり、また経営の発展と周辺諸科学の発展との相互関連によるところが多い。一応便宜的に言えば、
(1)軍事作戦に適用して成果を挙げたOR の流れ
(2)自動諸機器をつくり上げた通信理論・情報理論の流れ
(3)科学的管理理論もしくはIEの流れ
(4)コンピュータ・ソフトウエア開発の流れ
が、経営諸問題の解決に集約されつつあるのが現状といいうる。」

「システムと人間」
「システムと人間」は、日本能率協会の MSD(Manager’s Self Development)シリーズの第9 号として刊行されました。本書では、経営体内部で行動する人たちのシステム思考方法を次の三つに区分して、その必要性を説いております。
問題思考:問題をどう認識し、その原因・結果を多面的にどう考察するか。
方法思考:この問題解決の最適な方法はどれか。自分で代替案を構想し、案出できるか。
選択思考: 問題思考、方法思考によって選択された結論は、本来の目的に対して適切さをもっているか。それを評価する基 準をもっているか。最適なものを選択する判断力、決断力が問われる。
したがって、部下を持つ人のシステム化とは、
① 具体的な目標に沿うように人、もの、機械、サービス、情報を組み合わせ、
② その情報のそれぞれに高い信頼性を持たせ、
③ 目標実現のために最適な編成がなされ、
④ 相互の連携が図られ、
全体目標に沿うようバランスよく動くようにすること というこ とになります。
また、このための条件として、鈴木は
①これらの行動をまとめ上げている管理の仕方の基準が、仕事の単位単位に徹底し、
②仕事の進行状況や異常事態が確実に報告・処理され、
③自分の職場に受け入れられるもの、隣の職場に提供されるものが、それぞれ十分に管理されるような状態にあること、を挙げています。
では、これらの条件を達成するためには、どのようなことが管理する人には求められてくるか。
① 曖昧なものを、数字や図を使って具体化し、相互のコミュニケーションが正しく行われる状況づくり
② 潜在的な問題を事前に発見し処理する能力と、異常措置がスピーディに行える部下づくり
③ 職場全体が変化に対して急速・柔軟に行動を起こせるような、強い革新の気風を持った人間関係づくり
であると、鈴木は指摘しております。
このどちらの著書も、今から 40 年以上前のものですが、人と職場とシステムをめぐる問題は、常に古くて新しい問題であることを実感致します。と同時に、それ以上に、経営の場にシステムの問題が登場して間もない時代であるにもかかわらず、既にこれだけの洞察力で問題の核心を突いた鈴木の卓見に、改めて敬服いたします。 鈴木の旧著が、今もって読者を持ち得ているゆえんは、この辺りにあるものと思います。



◇現研の刊行物
「経営の設計」
「経営の設計」:昭和 45年、現研は御茶ノ水の東邦深沢ビルから本郷1丁目のビルに移転しました。 「システムの時代」、「システムと人間」という革新的で注目度の高い2冊の単行本の発刊のあと、教育研修の依頼、講演、シンポジュウムへの出向依頼、単行本・雑誌原稿の執筆依頼、対談依頼等は驚くほど増えていました。現研の事業は、企業内の教育研修、コンサルティング、講演、執筆活動が中心であり、ここまでのところ、事業は順調に進展を遂げてきたといってよい状況でした。しかし、組織としては、今後の事業の持続・安定化のために、自ら顧客に直接働きかけていくオリジナルなツールが必要な時期に来ておりました。 昭和 46 年、鈴木はこの時点こそ、現研を創業するに当たって計画しておりました考えの一つを実現する機会と捉えました。 当時のコンサルティング団体の多くは、それぞれ自団体が発行する雑誌、あるいは新聞など、有力な情報媒体をもっておりました。 独立した民間のコンサルタント組織である現研にも、何らかの情報発信ツールが必要でした。 この時までに、現研には独自に開発し、内部的に蓄積されてきたさまざまなソフトがありました。鈴木の計画は、これらのソフトを新しいマネジメントツールとしてシステマティックに発信していくことにありました。鈴木は、先ず、この計画の実現に向っての第一歩を踏み出すことにしました。 実は、このときの鈴木の事業計画はいくつかの段階を踏んで実現されることになっておりました。その第1段階がスタートすることになったのです。 先ず着手されたのが、「経営の設計」という名称の雑誌の作成でした。「経営の設計」誌は、当時としては異例の厚手の上質紙を用い、紙質、色、手触り等にこだわった非常に高級感のある A4 判の雑誌でした。紙面は、きわめて多量な情報を圧縮して、しかもそれらの情報の本質を損なわずに、どう価値あるものとして創り上げるか、すなわち高密度の情報体としてどう創り上げるか、その苦心と困難が伝わってくる、隅々まで工夫の行き届いた斬新な仕上りでした。 当時は、知識・情報の吸収は活字媒体が中心であり、また経営学がブームを迎えていた時代でした。 ここに掲載する内容について、鈴木は「伝聞情報ではありません。国際時代の広い視野を心がけ、時代を貫く理論を背景に、その調査内容や体験を打ち出したものです。時代の本質をつくものですが、悪い意味でのジャーナリスティックなものではありません。顕在問題を解決し、潜在問題を発見する、現実に苦労している方たちに役に立つかたちで、他で入手できない貴重な情報を、ささやかながら提示していこうとするものです」と述べております。 なお、「経営の設計」の原稿、調査報告の全ては、所長を初め、現研の内部の主任研究員、研究員グループによって執筆され、編集・制作も経験豊かな内部のメンバーが担当しました。

「現研『調査と展望』」
「現研『調査と展望』」:この第 1 段階では、もう一種、“マネジメントサービス”と位置づけられる刊行物の作成が計画されておりました。ここには、資料、研究会開催、調査リポート等を内容として、マネジメントに役立つ情報を類別し、忙しい方たちがコンパクトに通覧できるような体裁をとり、これらのサービスを通じて、企業の方たちと相互に人間的な関係を作り上げていきたいという鈴木の強い願いが込められておりました。このマネジメントサービスとして、 鈴木は「現研『調査と展望』」、現研ソフトウエア・カード、経営シンポジュウム等々、12のタイプのサービスを想定しておりました。 「調査と展望」は、経営の実態に即して、マネジメントに役立つ情報と、その背景にあるものを検証していこうという考え方に立った A4 判、見開き 4 ページの“情報紙”です。1 ページの中に何種類かの情報を盛り込み、写真を入れ、現研の活動近況報告にも触れて、企業の方々と現研の間に親しみや信頼関係を築いていきたいという鈴木所長およびメンバーの願いが託された毎月のマネジメントレポートとして、こちらも全て内部のメンバーによって作成されました。 計画の第2 段階は、これらのツールを用いて、現研というコンサルティング団体を企業の方々に広く認知して頂くことにありました。それをどのような方法で行うのか。この段階で鈴木の独自性が遺憾なく発揮されるはずでした。 しかし、ここで世界に大きな衝撃が走ります。日本ももちろん大きな動揺に見舞われます。ドルショックです。 この年の8 月、アメリカのニクソン政権は貿易のアンバランス是正のためにドルと金の交換の停止、輸入品への課徴金を決定しました。これは円の固定相場制の終焉を意味し、この予期せぬ事態の発生は、日本社会全体にただならぬ緊張と狼狽をもたらしました。企業もまた、いっせいに経費の削減に努め、組織体の自衛に集中しました。ここまで、前向きに、力強く活動してきた企業が、混乱の中で、兎も角内向きに、守りを固める姿勢に転じたのです。 これは、日本にとって、多くの人が予想し得なかった海外からの痛烈な一撃の第一歩でした。 鈴木は、この混乱状況の増幅が相当期間、日本を覆うとの展望のもとに、本事業計画のこれ以降の展開が厳しくなるとの結論をいち早く下しました。9 月、鈴木は本事業計画の打ち切りをスピーディに決定し、ダメージの最小限化を計りました。 この決定は、当時のメンバーにとってはいささか残念でもあったのですが、その後、日本を襲った衝撃や混乱を考えますと、今は、あの時のスピーディな決定に組織が救われたということを確信して おります。 「経営の設計」誌と「現研『調査と展望』」は、その後も刊行が続けられました。また現行の研究会、セミナーの基盤はこの時に確立されたものです。 このときの業務を通じて、現研のメンバーは創造への挑戦姿勢、状況判断力、洞察力、接渉力、仕事のスピード、質へのこだわり、連繋力、個と全体の調和等々、多くのことを修得しました。「あの体験がその後の自分をつくってくれた」と、後日、それぞれのメンバーが鈴木への感謝を口にしておりました。ここで当時のメンバーが鈴木所長の厳しい指導の下に修得した体質は、現研の資産として、その後のメンバーにも引き継がれてきていると思います。 IE、システム問題もそうですが、これらの問題とも絡んで、昭和40 年代の日本の産業には、他にもいくつかの特筆すべき潮流がありました。


昭和 40 年代前半の企業課題
◇情報問題
IBM360 と富士通 275
コンピュータ動向:この当時、日本のコンピュータ市場は、IBM360 と富士通 275 のメインフレームにほぼ占有されていました。とくにIBMは、世界的に絶対の力を有し、日本IBMも三菱グループに守られて、富士通との間には主にソフト面において、超えることが出来ないと思えるほどの大きな格差がありました。 しかし、日本には日本独自のソフトが必要ではないか、メインフレームの路線を離れて組み立てキットからの個人用の能率的ソフトが必要ではないか。コンピュータに関わる識者の間では、こういった見解の下に、基本ソフトの開発が待たれていました。
MISの導入
情報問題:IBM360が普及するにつれて、日本では、これからの経営課題の解決には、360 と同じ程度のことが処理できるコンピュータ・システムの導入を図り、MISに準拠することが重点となるというのが、経営の一般的なの考え方となって来ました。 この考え方の下に、企業はどの社も、MISの導入に躍起となり、どの社もコンピュータへの資金投入と人材育成を、経営の中心課題に据えました。
情報産業の実態
だが、当時の日本の情報問題環境の不備については、現研には次のような記述があります。 「情報処理のスピードが速いというだけで、メインフレームに過大な効果を期待することは安易に過ぎる。この安易な取り組みと合わせて、ソフトの非力、ソフト化を担う情報処理スタッフの非力を目の当たりにした時、なんともいえぬ暗澹たる気持ちになったものである」。 これは 2004 年当時、長野大学 産業社会学部学部長退任後、現研の特別上級主任研究員であった山本尚志の、当時を振り返っての述懐です。山本は7○5研のメンバーでもありました。

人の問題がカギを握る
そして、この当時の情報問題の実態については、前出の著書「システムの時代」の中で、鈴木成裕も次のように述べております。 「昭和 44 年、産業構造審議会の情報産業部会は、情報産業のあり方と政府がとるべき施策について、答申案をまとめた。その中には、情報産業の具体的な育成策が盛り込まれており、それに関連して情報産業の問題点がいくつか挙げられているが、この思想の背景には、明らかに本格的なシステムズ・エンジニア育成の意図がある。」という解説のあと、 「以上のことに触れたのは、今後想定されるこの種の産業の急激な伸長は、常に次のような事柄によって制約されること、そしてその具体的対策としては、企業内部での構成員の教育努力と、方法発見にまつところが多いということを述べたかったからである。 1. 頭脳グループの圧倒的な不足 2. システム利用技術の未開発 3. 膨大な必要資金 4. 企業外関連システムのは行性 5. 大型プロジェクトの運用のまずさ 6. 企業内外のシステム意識の欠如 7. 時代の進歩に無用な発想 8. 日本全体としてのマネジメント・ギャップ だが、このようなことは決して情報産業だけの問題ではない」と鈴木は言います。これらは、「これからの産業それ自体が、その離陸から発展過程の中で、常に遭遇する問題であり、最終的には“新しい人”問題に帰着するのである。すなわち、この人の問題、群としての人、リーダーとしての人、評価者としての人、つくる主体としての人、利用する人・・・のシステム認識に深く関わり合ってくる。」

昭和44 年 共著「ビッグ・プロジェクト」 -システム化時代の成長戦略-(坂元正義編著 ダイヤモンド社)
◇未来への挑戦――ビッグ・プロジェクト
予測とプロジェクト
ビッグ・プロジェクト:「システムの時代」には、第(Ⅳ)章に「予測とプロジェクト」という項があり、ここで鈴木はプロジェクトの巨大化は時代の要請であり、それに連動して進展を遂げた未来予測技術、情報技術、システム工学の流れを展望しております。 本項の中で、鈴木は、「現在のように未来問題が騒がれる以前から、企業は常にある目標としての未来を考え、そこに到達すべき自社の像を想定し続けてきた」と言います。 しかし、「社会が複雑化し、かつ企業にとっては新しい製品の開発に長期の時間を要し、膨大は設備投資と、すぐれた頭脳の投入と、そして生産諸手段の開発が必要になった現在においては、予測それ自体が的確か否かが、大きな社会的影響を持ち始めてきた」と、当時の企業努力が向かっていく方向と、その実現に伴う予測の難しさに触れております。 そして、例として、IBM 社が IBM360 の開発に 4,50 億ドルを投入、これが如何に巨額であったかは、マンハッタン計画(第2 次大戦中の原子爆弾開発計画)の投入費が 20 億ドルであったことからも窺えること、またアメリカ航空宇宙局の予算はアポロ計画において年間 239億ドル以上、アポロ 10 号のみで 3 億 5 千万ドルが投入されたことを挙げ、企業の命運、あるいは国家の威信をかけるような主題を扱うプロジェクトにおける確かな未来予測力、情報力、システム力の重要性を指摘しております。

未来へ挑戦する意思決定
なお、鈴木は昭和 44 年刊行の坂元正義先生の編著による「ビッグ・プロジェクト」-システム化時代の成長戦略-(ダイヤモンド社)において執筆陣の一人として、第7 章「未来へ挑戦する意思決定」-IBM 360シリーズの開発の背景-を担当しております。 本書では、ビッグ・プロジェクトを“国家的な規模の大きさをもち、その実践のためには巨額な国家資金投入と諸分野の専門家の動員 その間に科学技術の著しい発展を必要とし、実施期間があらかじめ予定されているようなプロジェクトである そして、ビッグ・プロジェクトは、一般には未来挑戦的であり、野心に満ちた性格を持ちながら、またつねに失敗の危険性の高いものである”と解説しております。 また、本書には“アメリカの代表的なプロジェクト TVA 計画(1933)、マンハッタン計画、アポロ計画、そして特色をもつ企業プロジェクトの成功の条件を内在的に検討、その発展系列の分析を通じて日本の国家的、企業的各プロジェクトへの示唆を得ようとの意図の下に刊行されたものである”との記述が付されています。 執筆を担当した第7 章において、鈴木は、プロジェクトの本質とは、「未来に挑む行為であり、現在の中に未来を実現させようとする行為であり、その具体的目標を定められた時間の間に定着させると消滅する」との考えを提示しております。 そして、未来への挑戦とは、未知な部分を含む行動であり、そこには絶えず意思決定の誤りと、それに基づく行動の誤りが含まれる危険性があることに言及しております。 さらに、私企業におけるプロジェクトは、政府機構や軍事機構が行うプロジェクトとは目標の絶対性や絶対完遂度など微妙な点において異なることに触れ、「企業のプロジェクトは常に製品に向かって集約される。したがって、プロジェクトの推進につれて社の行動の全容が姿を現すことになる。IBMのプロジェクトもそうである」との考え方を示します。 以上の前提に立って、本章では、1960年代に入って世界最大のコンピュータ・メーカーとして順調に業績を伸ばし続け、前途も洋々たる IBM 社にあって、首脳陣が「既に獲得した地位は、新しい手段によって革新されなければ守りえない」との認識に立ったこと、そしてこの認識の下に、技術への挑戦、生産技術、情報の統一化、競争社会に配慮した法規制への対応等々に力を集結したことについて詳細に解説し、未来への挑戦において、意思決定がいかに重要であるかを指摘しております。 ビッグ・プロジェクトはぼう大な単位業務をもち、それを効率的に働かせるために未来予測、情報一元化等の技術体系が形成され、全体をシステムとして捉えることでシステム工学の発展を促しました。システム思考による意思決定の重要さへの覚醒にもつながりました。 そのことを、当時の現研のメンバーは、本書を精読することによって、学び、再確認したものでした。

◇品質管理の徹底と成果
品質管理:1951年(S.26)品質管理の第一人者といわれるアメリカのデミング博士(Dr.Deming)が来日、これを記念して品質管理の功績に力のあった企業及び個人を表彰するデミング賞が設置されました。同氏の著書「品質管理」も翻訳・出版されました。 これは、「安かろう、悪かろう」と言われた日本製品が良質化を目指す転換の大きな契機となりました。この流れの促進には、通産省のほか日本能率協会、日科技連、日本生産性本部等の団体が中心的な役割を果たしましたが、各企業もデミング賞の受賞を目指して大きな努力を払い、その結果、日本の各産業分野で品質管理は目覚しい成果を挙げました。 この現場の品質管理思想は、昭和 40 年代の作業単純化計画、システム単純化計画、QC 運動、ZD 運動、5S 運動に繋がっていき、「良い製品をつくる」ための原則論として、現場の人たちの意識改革を促す役割を果たしました。

◇小集団活動
小集団活動:鈴木は、これらの品質管理運動を効率的に展開するためには、小グループによって現場の活動をスピーディにし、現場を活性化すること、現場の個々人の自主性を重視することが重要であるとの立場をとり、「小集団活動」というコンセプトの下に、TQCとは異なる小集団計画の編成を推進しました。 小集団活動には、どの企業も力を注ぎ、成果を挙げたグループには報奨金や休暇の付与、海外研修への出向等の措置が取られました。 品質管理運動は、小集団活動と結びつくことで、より確かな成果を結実させました。 しかし、企業体の存立という立場に立つなら、現場の能率性、効率性の保証、現場の基本活動の徹底だけでは不十分です。小集団活動を行う企業には、小集団活動を管理・推進し、同時に、全体を一つの集団として新しい変化に対応し、いかに振舞うべきかの論理と行動も必要です、それが個々の企業という存在の将来の決め手となる筈です。

昭和 40 年代後半の企業課題
◇新社会、新産業構造への準備
国際化
海外からの衝撃:折から、時代は 70 年代安保闘争・その惨澹たる結末と若者の意識変化、レジャーブーム、個人の価値観の多様化と市場の多様化、公害問題の深刻化等々、多くの新事態に見舞われていました。ベトナム戦争(1960~75)は泥沼化の様相を呈し始め、日本の前途にも、どこか暗い影を投げかけていました。 昭和 43 年、日本は GNP(当時)世界第 2 位を達成、45 年に人口が1 億人を突破、そして昭和 47年には、「日本列島改造論」を掲げて田中角栄が首相に就任しました。その前年 46 年にはドルショック、48年にはオイルショックが発生しております。日本が国際的体質への切り替え、芽生え始めた自信など、古いものと新しいものの選択の間で大きく揺れ動いていた時代でした。 そして企業という大きな集団を管理する思想も、画一的な集団管理の思考・方法ではいずれ行き詰ることは明らかでした。 S.47 鈴木成裕著「小集団の論理」(日本実業出版社)刊 S.47 鈴木成裕著 「集団学入門」(社 日本能率協会)刊

「小集団の論理」
「小集団の論理」に関しましては、鈴木の古くからの知人である三原田 栄氏(経営工学研究所次長 当時)が、「IE」誌(1972 年 5月号)に「効率的小集団の経営システム」のタイトルで書評を書い て下さっております。 その中からの抜粋です。 「~先ず、本書の書名から、小集団とは独立したベンチャー・ビジネスと直感的に受け取られようが、内容は決してそうではない。筆者は、小集団のパターンとして、独立の小集団(小規模の会社)、組織の中の小集団(会社内部の課や係といった組織単位)、一時的単一小集団(プロジェクト・チームなど)、一時的部分型小集団(協同プロジェクト組織)の4つをあげ、それらの小集団の本質、小集団問題の背景、大集団と小集団の関係、小集団におけるリーダーシップ、小集団の技術・手段、小集団の手がかりなどを、多面的・動態的に論じている。 また、著者は、価値観の多様化、情報化社会と技術高度化に伴う専門化現象、未知市場への挑戦・開拓、参画経営、人間主義経営などの今日的な経営の環境条件は小集団指向を要請しているとし、経営的に独立している小集団にせよ、最小のエネルギーまたはインプットで最大または最適のアウトプットを得られる小集団の機能化、システム化、精鋭化をいかに進めるべきかについて、著者特有の筆法で説いている。中でも、人間の意識、集合の存在、その不安定性、動因となる要因の存在などを基礎とする「場」と「野」の理論は、筆者独自の論理展開の小宇宙を形成しているようだ。」 そして、むすびでは「これからのベンチャー・ビジネスを志す人びとや既に独立している小集団のリーダー、または幹部クラスの人びとはもちろんのこと、企業規模の大小を問わず、多重組織の中の小集団のリーダーである中堅管理者にとっても、本書は一読に値する恰好の書であろう。」と、当書籍を推奨して下さっております。

企業と人・価値・能力
集団学入門」も、日本能率協会の MSD シリーズ中の 1 冊として刊行されたものです。本書の中で、鈴木は「ある意味で、70 年代は他の年代よりも、わが国においては、前の年代の整理と、次の年代への転換の準備という過渡性が強い」。その中で、どの集団も確実に80年代を指向して動き始めていると指摘し、続けて「そして、集団を動かしているひとりひとりの価値観問題は模索につぐ模索ではあるが、次第に 70年代を脱皮しようとしている」と、指摘しています。 70 年代は、確かに、成長路線を走り続けてきた日本、そして日本企業にとって大きな転換の準備期でした。否、一面では既に転換は始まっていた、と言っても良い時期だったと思います。 その意味で、上記2冊の著書は、鈴木が「集団学」という立場に立った重点管理思考によって、今後、大きな転換期を迎える企業の経営展開の筋道を明らかにしたいという意図の下に執筆されたものということも出来ます。 さらに鈴木は続けます。 「このような状況の中で、急進的な状況破壊主義と、新しいものすべてに目をそむける新保守主義とが登場してくる。ある意味では、一見、対立するこの二つの考え方の底の方に、共通のものとして、こうあらねばならない人間像よりも、こうある人間像の主張というものが強く浮かんできている。」そして、「ただ、このような激動と、離合集散と、崩壊の過程の中での集団の挙動は、19 世紀的な衰弱の過程ではなさそうである。少なくとも、われわれの場合は、緊張と不安の中で新時代形成の集団の統合過程、構造変革過程に入りつつあると考えてよい。この事態に即応するためには、自分の集団の生み出す価値と、現在及び将来の能力の機能化の二つ目を向ける必要があるだろう。」 この見解が、当時の時代状況とそれが日本にもたらす影響を鋭く洞察したものであったことは、同じく「集団学入門」の「小集団の論理と大集団の論理」の項に記述された内容からも伺えます。 「さて、私は現在の経営の統合、合併、分離、提携などの大きな流れの根本にあるものは、新社会、新産業構造への自社の適合化と、本来業務の追求と効率化、再展開の問題であると思う。そして、このことを別の見方で見ると、一つは自分の社の総体的な核化-小集化であり、また機能分化に伴う各単位の小集団化であると思う。同じように、他の小集団との組み合いの問題であると思う。そして、社会的には、これを支えるものは機能分化と価値観の多様化ではないかと考えている。つまり、大集団化と小集団化は、これからの経営体系の中では相互に関係のない独立したものではなくて、大集団化のために内部小集団の機能化が行われねばならず、大集団の総体的小集団化は外部小集団との適切なグループ化が前提になると思われる。多様化する市場への多角的な進出もまた、当然、小集団による開発活動を絶対必要とする事態になっている。」




人間主義の登場とマネジメントの変質
なお、この時代を象徴する新たな産業動向としては、日韓基本条約(S.40)に基づく韓国製鉄業への日本の全面的な資金・技術協力、富士製鐵と八幡製鐵の合併による新日本製鐵の誕生(S.45)、また造船事業の韓国へのシフトも進行しました。そして組織の中に人間主義が登場してきたのもこの時代です。 この書は経営・管理という意味では、現場ラインの強さで対処しようとしてきた日本企業の在来思想を超えて、企業全体としてどう動くべきかを示唆し、スタッフ業務というものに関心と重点を移すことを推進すべき時代が来たことを告げている書である、という言い方をしても良いものであると思います。
◇海外視察
海外調査:昭和 45 年、関西経営管理協会が企業の方々に参加を求めて、欧州への海外視察を企画・主催いたしました時、鈴木に団長としての参加依頼がありました。当時は、未だ海外旅行が一般化しておらず、庶民にとって垂涎の的であった時代でした。訪問先は仏、英、西独、スイス等、欧州の主だった国がほとんど網羅されておりました。ご参加された方々は、日本全国の企業のトップや、経営幹部の方々でした。 当時、円は未だ 360 円。海外への渡航者の持ち出しの円は 10 万円までと規定されていたと記憶しています。所長の海外出張は、現研メンバーにとっても大きな出来事でありましたため、ほとんど全員が羽田まで、夜間便で出発される所長を見送りに行きました。ご家族も、全員で来ておられました。 帰国した所長の持ち帰った荷物のほとんどは、海外諸国の企業や製品のパンフレット、関連諸機関発行の調査リポート、図書、雑誌、新聞などで、それがいずれも当時の日本のものに比して、カラフル、贅沢なものであることに驚かされました。その後、47年に、同協会のご依頼で鈴木は再び、団長として海外視察に出かけております。 しかし、鈴木もそうでしたが、この当時の企業の方々は、海外の多くの情報は既に相当持っておられたと思います。日本の当時の新知識・情報の吸収力は猛烈で、多くの企業が必要な情報の入手には積極的に取り組んでおりました。 海外視察は、その情報を実地で確かめることに中心を置いたものであったこと、それが大変有効で有り難かったということを、後日、鈴木は、海外に出張するメンバーに向って申しておりました。

◇「経営新時代」
NHK教育テレビ「経営新時代」出演:昭和 49 年、鈴木は日本放送協会より、午前7時~7時30分放映の「経営新時代」という番組に、対談の聞き手の立場として出演依頼を受けました。5 回程の出演だった筈ですが、この正確な記録が、現在、当所内のどこを探しても見つかりません。従って、本記述には、あるいは記憶違いの部分もあるかもしれません。 同対話のお相手は、1972年のミュンヘンオリンピックで日本の男子バレーに金メダルをもたらした松平康隆監督、三菱総合研究所の牧野昇先生、当時のヘキスト合成㈱社長大門正輝氏、横浜ゴム㈱企画室長貞政忠利氏等で、日本企業が抱える経営マネジメント問題、リーダーシップ・意思決定問題、科学技術の現状と将来展望など、当時の時代性を反映した真剣な好番組でした。 「経営新時代」という番組名は、日本の企業にとって昭和 40 年代がどのように位置付けられる時代であったかを象徴する立派な名称であったこと、そしてこの対談の内容も、その後の日本企業、日本人の特性を鋭くついたものであったことを、40年近く経った今、改めて実感しております。 ここで、昭和 40 年代、所長鈴木成裕の指揮・指導の下に現研が開発したコスト計画(DC 計画)方法について触れておきます。

◇ダイナミック・コスティング計画
ダイナミック・コスティング計画(DC 計画):企業にとって、固定費は常に一定額を計上し続けなければならない負担の高いコストです。ここを如何に下げるか。本計画は、行動を詳細に分解し、行動計画を作成する過程で、そこに発生する費用を固定的に捉えず、調整・削減する工夫をする必要があるだろうという発想に基づくコスト削減案です。 例えば、企業が新たな開発に要した費用は、それが事業展開されない限り回収できず、経営にプラス効果を生み出しません。あるいはコンピュータ要因として育てた人間が他所に移籍してしまった、これも管理のまずさが経営にプラス効果をもたらさない例です。このように、減価償却費や人件費等の固定費には、経営にとって成果をもたらさない行為による費用が含まれてきます。これらのコストを埋没コストといいますが、この埋没コストを極力発生させないように、常に機会コストを考え、ダイナミック・コスティング化することがマネージャーには経営管理能力として問われます。DC 計画は、この認識に立って、コスト削減を経営管理問題として捉え、行動計画と連動して考えていく方法です。
昭和 40 年代総括――転換を促す事態の発生
* 昭和 40年代の日本、及び日本を取り巻く状況の中で、その後の鈴木成裕所長の発想、創造活動、そして現研の活動に少なからぬ影響を及ぼした問題、事態、事項を付記します。
●ドルショック(1971・8):米ニクソン政権は貿易バランス是正のためにドルと金の交換を停止。輸入品に一律10%の特別課徴金を決定。これは日本にとって1ドル360円の固定相場制の崩壊を意味した。この年、円は1ドル308 円に切り上げられた。
●変動相場制(1973):この時点まで、紙幣は金と兌換することとタイトに結びついてきたが、本格的変動相場制への移行によって、金の保有高とは独立した紙幣の動きが発生。いわゆる悪貨による良貨の駆逐の時代が到来したのである。これ以降、政府には金が不足すると紙幣を印刷すればよいという風潮が定着。だが一方、円の切り上げによって、ドルによる日本の外貨準備高は増加した。同制度発足当時の円の対ドルレートは、277円。
●日本列島改造論(1972):日本にとって、71 年のドルショックは、50 年代からの日本の高度成長に終止符を打つものと受け止められる大きな衝撃であった。翌年、日本列島改造論を掲げて田中角栄が首相に就任。日本政府は総需要拡大のために積極経済政策を推進、高い経済成長率を維持。だが、不動産、株式への投機が過熱、インフレが進行。土地値の高騰の結果、職と住の分離・遠距離化が加速。郊外を中心に大規模団地、大規模商店、スーパーマーケットが乱立。また、相対的に一人当たり所得も高水準となった。
●石油ショック(1973):OPEC は石油価格の値上げ、産出量の削減、非友好国への禁輸を発表。世界第2 位の石油消費国である日本にとって、安価な産業資源としての石油の不足は、原材料の不足、エネルギーの不足に直結してコストを押し上げ、企業の生産活動を直撃した。庶民生活も打撃を受けた。ガソリン、灯油、電気、交通費の値上げ、物不足と物価上昇が、そろそろ「飽食の時代」といわれ始めていた日本社会に大きな衝撃と異常事態を生んだ。
●狂乱物価・低成長(1973~ マイナス成長、消費者物価24.4%上昇のインフレ):原油価格の高騰(73・10・1 日:1 バーレル 3ドル、74・1・1日:同 11ドル)によって、国際収支の悪化、経済成長の鈍化、異常なインフレが発生。原油の高騰が輸入原材料コストを押し上げ、物価が上昇。さまざまな便乗値上げを生み、狂乱物価という言葉を流行させた。 現研報告書類(昭和 40~45 年) 既に 71 年、ニクソンショックによって、日本の高度成長時代は終焉。だが、表面的には、政府の景気刺激策によって、成長率は72年:9.0%、73 年:8.8%を維持。しかし、次に打ったインフレ鎮静化の金融引き締め策で公定歩合を引き上げ、この結果、経済成長率は74年:-1.2%と戦後初のマイナス成長を記録。その後、75年:2.4%、76年:5.5%と成長率は鈍化。
●環境汚染問題:昭和 40 年代前半、日本の鋳物産業は未だ健在であった。鋳物はキューポラで水を蒸留し、美しく丈夫な製品を速くつくることが出来、かつつくり直しが可能であるために、多大な運転資金を必要としない産業。埼玉県川口市は鋳物の町として有名であったが、ここで、鋳物に使うメッキによる水質汚染という環境問題が表面化。また、電気洗濯機の普及と洗剤の使用、排水によって、河川の発泡問題が発生したのもこの頃であった。 この環境汚染問題に、鋳物の場合は工場移転によって、洗剤の場合は技術開発による界面活性剤の改良によって企業は対応。これは、当時の最も典型的な環境問題対応策であった。
●団塊の世代:戦後の第一次ベビーブームと言われた昭和 22 年から 24 年生まれの人たちは、その数の多さから、堺屋太一氏によってこのように命名された。この世代の中卒者、高卒者、大卒者は丁度日本の高度成長期に就職し、日本の経済成長を支え、そして日本社会の新しい消費行動の牽引力となった。また 70 年代の映画や音楽、そして漫画やアニメ等、いわゆるサブカルチャーの先導者であり、昭和 40 年代以降の日本社会の新しい潮流に大きな影響を与え続けてきた。とくに昭和40年代の車、住宅、レジャー関連商品、大型家電、ファッション等々への消費行動は、日本の消費マーケットの規模を大きく拡大させ、昭和 26 年生まれまでを含めて、マーケット・サイズとしては 1000 万人とみなされるとも言われてきた世代。 団塊の世代は、就学年齢の時代から絶えず厳しい競争にさらされ続け、企業組織においても、丁度企業が人手を必要としていた時期に大量雇用されたために、組織内でも絶えず、競争の洗礼を受け続けることを余儀なくされた世代であった。 この世代の去就は、常に団塊の動きとなって、今日においても人口動態と結びついて、日本社会、日本企業の動向に影響を与え続けている。





後 記: 2012年2月15日、当現研ホームページ冒頭でご報告致しました通り、㈱現代経営技術研究所所長 鈴木成裕は肺炎のため永眠致しました。 ここに、亡き鈴木への追悼の意をこめて、昭和40 年より47年間にわたる鈴木の活動を通して、とくに現研の事業活動を支え、またその活動を導き、特徴づけてきた思想を中心に、その足取りを辿ることを試みることに致しました。今回は第Ⅰ回として、昭和40年から 49 年までの10 年間を対象の期間と致しました。本記述は、実は2004 年、当時、長野大学産業社会学部学部長を退任し、現研の特別上級主任研究員でありました山本尚志の執筆・指揮の下に、4 月~9 月に、丁度40 周年を迎えます現研のために「現研活動史」としてまとめられましたものを原本としております。この度は、それに鈴木の活動のいくつかを加え、より時系列的な流れに沿うことを試みたのですが、鈴木の活動範囲があまりに広く、一部に、確実な裏づけを膨大な資料群から見つけ出すことを現段階では諦めざるを得ないものも発生してしまいました。その意味では、本記述は、未だ不完全なものと言わざるを得ません。しかし、今、何か一つの形をもって、鈴木を追悼したいという所員一同の強い願いから、ここに、掲載に踏み切ることに致しました。